Written in Japanese(UTF-8)
2014.8.30
INASOFT
2014.8.30
INASOFT
/トップ/いじくるつくーる/ダウンロード/WebHelp/ヘルプトップ/
本ソフトウェアの開発は終了しています。ヘルプに記載されている情報も古いものになっています。
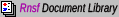
文章保管庫
【お題目】 略語(2000. 4. 9)
作者がちょっと気になっていた略語を集めてみたページです。
最初は略語とコードネームを集めて、開発中はWindows 95はChicagoでWindows 98はMemphisでWindows 2000はCairoと呼ばれてたんだよ〜とかってちょっと知的に飾ってみようと思っていたんだけど、あんまりネタもないのでやめました。
(R)
Microsoft(R) についてくる (R) ってなんなんでしょう? って疑問を持っている人は多い様子。
実はこれは Registered Trademark の略。日本語で言う登録商標なんだそうな。
(Remark だ、って話も聞いたことがあるような気がします)
(C)
(C)Copyright の (C) ってなんでしょう? って、これはそのまんまCopyrightの略。
日本語で言う著作権の意味。
ちなみに、海外では半角カタカナの小さい「ゥ」が、これの文字コードになっています。
TM
これもよく、なんかの名前の後ろに付いてきていますが、これはTrade Markの略。
日本語では商標という意味です。
NT
最近 Windows 2000と改称してしまった Windows NTですが、僕はNTをNetworkの略なんだと思っていたらなんと、New Technology の略なのだという。
知らなかった…。
ところで、Windows 2000の起動画面に出てくる「Built on NT Technology」ってどういう意味だろう...?
「Built on New Technology Technology???」
→この記事を書いて数年後、Microsoftは、NTは「N-Tenの略である」ことを明らかにしました。
BASIC
BASIC言語は簡単だから Basic(基本)の事なのかなぁと思っていたら、見事に外してしまった…。
Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code が本当の略語なんだそうだ。
しかし、基本という意味のBasicに、無理やり意味を当てはめた、というあたりが正確らしい。
COBOL
C言語ってCOBOLの略なんだよ〜などとバカみたいなことを言っていた某友人がいましたが、真っ赤な嘘。
C言語は略語じゃないの。
ちなみに、COBOLは 事務処理用プログラミング言語で、Common Business Oriented Laguage の略です。
FORTRAN
コンピュータ言語の関係が続いたので、これも載せておこう。
FORTRANはIBMが開発した化学技術系算用のコンピュータ言語で、Formula Translation の略です。
LISP
去年、大学の授業でお世話になったこの言語。
人工知能用として開発された高級言語で、List Processing の略で、マサチューセッツ工科大学で開発されたんだそうだ。
C言語
昔、C言語が何の略だか調べたくて、いろんな略語辞典で調べたんだけど、どこにも載ってない…。
で、結局「C」というのは略語ではなかったというのがオチ。
元々、ベル研究所では、その頭文字を取った「B言語」が使われていたのですが、それを発展させた言語として生まれたのが「C言語」。Bの次だからCというかなり安易なネーミングだったのでした…。ちゃんちゃん。
ちなみに、C言語をさらに発展させた言語はD言語にはならず、「C++」となったというのは有名な話ですね("++" は、C言語の「インクリメント」を表す演算子です)。
ちなみに、Pascal も アセンブリ言語 も略語ではない様子…。(あたりまえ)
NTT
日本で最大手の電話会社。
Nippon Telegraph and Telephone Corporation の略なんだそうだ。これは知らなかった…。
N だけなんで日本語の略なんだろう?とか言わないように。
DoCoMo
ドコモの携帯を持っていると生徒に言ったら、「コドモが好きだからドコモにしたんでしょ? このロリコンが」と言われてしまったことがあるが、全く関係ねーじゃねーか。そんなことより受験生なんだからもっと勉強しろ。え? もう受かったんだ。じゃ、いいや。
Do Communications Over The Mobile Network の略なんだそうだ。なんか複雑だ。
で、DoCoMoの日本語名称はNTT移動通信網株式会社だったよね。
NEC
Nippon Electronic Corporation の略ってのは有名。これもまたなんで N だけ日本語なんだろ?
ま、いいか。JTT とか JEC とかだとなんとなく変なような気もしてきた。
ところで、"NEC Corporation" ってどっかに表示されなかったっけ?
つまり、"Nippon Electronic Corporation Corporation" ってことかな。
DVD
Digital Versatile Disc の略というのが現在の説。
最初は Digital Video Disc の略だったらしいが、では DVD-Video はどうなっちゃうんだ?ってことになったり、いや、DVDは略語ではないんだとか言ったりと、DVD を管理している団体やその取り巻きの会社でかなりのもめ事があったとか。
lParam と wParam
ピュアなWindowsアプリを作っているプログラマなら、一度はお目にかかったことがあるだろうという変数名。
Windows大親分が、子分である各アプリケーションに対してメッセージを送る際、そのメッセージに付随するパラメータを伝える役目を果たすのがこのwParamとlParamなのだ。
Windowsには多数のメッセージが存在するが、その大半が「ここがクリックされました」「このボタンが押されました」「ウィンドウが作られました」の処理をする程度であるが、Windowsから送られてくるメッセージには「バッテリーが切れそうです」「今ユーザーがノートパソコンのふたを閉じちゃいました」なんてメッセージもあったりする。中には「ユーザーが飛行機かなんかに乗ったんだろうと思うけど、ユーザーがいきなりコンピュータを閉じたんで、今は復帰直後です。失われているデータがあったら、ユーザーに提示しなさいね」なんていうのもあったりする。じつに多種多様である。
さて、問題はwParamとlParamが一体何の略か?ということなのであるが、これにはWindowsがまだ16bitだったころに原因がある。
windef.hを覗いてみてまずわかることは、WPARAM型はUINTに、LPARAM型はLONGに typedefで定義されているということだ。
そしてさらに同ヘッダファイル内で UINTはunsigned intに、LONGはwinnt.h内でlong型にtypedefで定義されている。
現行のWindowsは32bitのOSということになっているので、int型は short int とでも明示しない限り32bit変数になってしまう。
要するに、long int も int もサイズが同じになってしまうというわけだ。
よって、WPARAM も LPARAM もサイズは同じである。
しかし、Windows 3.1 時代、int は16bitだった。すなわち UINT = unsigned int は16bitだったのだ。
Windows 3.1プログラミングでは、UINTはWORD型と等しくなる。
これが、wParamの w になっているというわけだ。
現行のWindowsではwParamは32bitのUINTなので、本来はMicrosoftの型プレフィックスに従いdwParamとでも書かれなければならなかったのだが、そうすると色々混乱が生じるとでも思ったのだろう。確かに実際、WPARAM型がDWPARAM型への置き換えを要求されると、プログラムの書き換えが膨大な量になってしまう。
そういうわけで、wParamはWORDではないが、WORD型のパラメータの名前だけが残されたというわけだ。
ちなみにlParamの l はlong型整数であることを示し、Paramは「パラメータ」の略であることは言うまでもない。
ところで、32bit化に伴って p という型プレフィックスが lp と等価になってしまったという話もあるが、それはまたの機会ということにしておこう。
URLに使われる略語
jp…日本 uk…イギリス ru…ロシア
ne…ネットワーク関連 co…会社関係 go…政府関係 ac…大学関係 or…その他の組織 gr…有限会社以上の法人組織 net…ネットワーク関係 com…会社関係 org…組織関係 edu…教育関係 gov…政府関係
int…国際機関? to…トンガに置いてあるサーバーらしいです
これからも増えるかなぁ?
※このページは、ソフトウェアに付属のヘルプファイルをWeb用に再構築したものです。大部分に自動変換を施しているため、一部は正しく変換しきれずに表示の乱れている箇所があるかもしれませんが、ご容赦下さい。また、本ドキュメントはアーカイブドキュメントであり、内容は「いじくるつくーる」最終公開時点、あるいは、それより古い時点のものとなっております。一部、内容が古くなっている箇所があるかと思いますが、あらかじめご了承下さい。
※このページへは、自由にリンクしていただいてかまいません。
このページに関するご意見の受け付けは終了しています。




 略語
略語